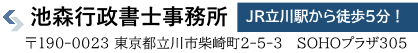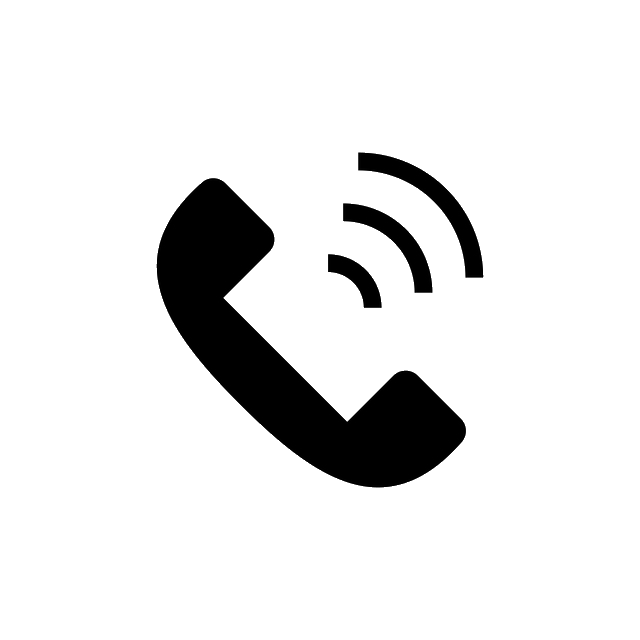「般・特新規」とは〜その注意点を解説

ここでは、「般・特新規」について、その注意点を解説していきたいと思います。
1.「般・特新規」とは
「般・特新規」とは、名称のとおり新規の扱いですが、すでに許可を受けている場合であって、その受けている許可が一般のみ、もしくは特定のみという場合において、これに一般、特定を申請する場合となります。
なお、一般⇒特定への変更に関しては、許可要件が特定のほうが難しいので(専任技術者、財産的要件)、要件をクリアできるかをまず検討する必要があります。
許可の要件についての解説は建設業許可の要件の記事をご覧ください。
2.「般・特新規」の場面
般・特新規がどのような場面で出てくるかといいますと、例えば、
1. 下請けとして工事を受注してきたが、今後は元請として大きい工事も受注したい。
(一般⇒特定へ切り替える)
2. 許可の期限が迫っているが、特定建設業の資産要件を満たすことができなくなった。このまま特定での更新はできないが、一般建設業の資産要件は満たせる。
(特定⇒一般へ切り替える)
3. 専任技術者が交替するが、新たな専任技術者は一般の要件は満たせるが、特定の要件を満たせない。
(特定⇒一般へ切り替える)
というようなケースがあるかと思います。
具体例としては、以下のような場合になります。
注意点は、「般・特新規」に該当するのは、受けている許可が一般建設業のみ、もしくは特定建設業のみという場合だけです。
(1)「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
| 許可を受けている業種 | 「般・特新規」申請後の許可業種 | |
|
例1) |
 |
〇大工工事業(特定)に切り替え |
|
例2) |
 |
〇大工工事業(特定)に切り替え |
|
例3) |
 |
大工工事業(一般) |
(2)「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
| 許可を受けている業種 | 般・特新規申請後の許可業種 | |
|
例1) |
 |
建築工事業(特定) |
|
例2) |
 |
建築工事業(特定) |
|
例3) |
 |
〇建築工事業(一般)に切り替え |
3.「特定」のみ⇒ 「一般」への切り替え
特定のみ⇒一般への切り替えの際に注意点ですが、上記の(2)の具体例のうち、特定のみを受けていて、その全ての業種を一般にするな場合ですが、この場合は、既に持っている特定の業種が無くなってしまうため、特定を一旦、廃業扱いとされます。何も許可が無い状態になってしまうので、般・特新規ではなく「新規の扱い」になります。
ただし、建築工事業(特定)、左官工事業(特定)のみから、どちらかを一般に切り替える場合は、何も許可が無い状態になるわけではないので、当該特定を廃止とした上で般・特新規となります。
「新規の扱い」と書いたのは、申請区分として新規とするのか、提出書類からみて実質的に新規と同じなのか、この扱い方に違いがあるためなのですが、詳しくは以下で解説しております。
まず、同一の工事業種について、一般⇒特定に変更する場合と、特定⇒一般に変更する場合では、元の許可がどうなるのかの扱いが異なる重要な3つのポイントがあります。
A)一般の工事業種について、これを特定に変更する場合
⇒従前の一般の許可は特定の許可を得ることで効力を失う。
(建設業法第三条第6項より)
B)特定の工事業種(複数)のみを持っている場合、この一部を一般に変更する場合
⇒当該業種は廃止とし、般・特新規として一般を申請する。
(国土交通省の建設業許可事務ガイドラインより)
C)特定の工事業種(一つ又は複数)のみを持っている場合、この全部を一般に変更する場合
⇒全ての業種を廃業とし、新たに一般を申請する必要があるので、般・特新規ではなく新規に該当する。
(国土交通省の建設業許可事務ガイドラインより)
上記のB),C)については、許可の取消事由(経管、専技についての許可要件を満たさない、又は、欠格要件の一部について該当する等)に該当することによって許可を継続できない場合に限られますが、許可要件の内、財産的要件と誠実性の要件については、含まれていません。
逆にいうと、特定で必要な財産要件(資本金が2千万円以上、純資産が4千万円以上など)を満たさなくなったので、許可の更新の際に特定での更新ができずに一般に変更するような場合は、取消事由には該当せず、B),C)いずれも、特定を一旦廃止または廃業するということはせずに、般・特新規で申請するということになります。
なお、C)については、全ての特定を廃業とするので一時的になんの許可も持っていない状態になるので、新規に該当するということと理解されます。
分かりやすくまとめると、
■同じ業種で一般⇒特定
・・・般・特新規の申請により、従前の一般の許可は効力を失う。
■同じ業種で特定⇒一般
・・・その業種は廃止してから般・特新規を申請。
■全ての業種で特定⇒全てを一般
・・・全ての業種を廃業してから、新規で申請。
※廃止・廃業は、経管、専技についての許可要件を満たさない、又は欠格要件の一部について該当すること等により、許可を継続できない場合に限る。
となります。
4.「般・特新規」と「新規」の違い
「般・特新規」と新規では、何が異なるのでしょうか?
どちらも「新規」という言葉を使用していますが、実態としては、「般・特新規」は既に一般か特定の許可を持っているわけですので、業種追加に近いと言えます。しかし、建設業許可は、一般建設業か特定建設業の区分毎に、さらに工事業種の種類ごとに許可を受けるものですので(建設業法第3条)、一般、特定の区分が異なるということは、新しい許可を受けることになりますので、やはり新規の許可ということになるのです。
東京都の場合
手引きによりますと、提出する資料について以下のようになっています。
「「般・特新規」申請では、一部業種のみ変更・追加する場合は追加申請と同一の書類であり、全業種を変更・追加する場合は新規申請と同一の書類が必要。」
これは、一般⇒特定の場合と特定⇒一般のどちらであっても、一部の業種の変更・追加は業種追加と同じ扱いですが、全部の業種を変更・追加する場合は、新規と同じ扱いになるということですので、この場合は、一旦廃止・廃業となるために、新規申請と同じ扱いになるということなんですね。
但し、あくまで手続き上は般・特新規として申請するということです。
なお、従前の業種について廃業届は、現時点では提出不要となっています。
これに対して、大臣許可の場合はどうでしょうか。
国土交通省の手引きによりますと、般・特新規は業種追加と同じ書類の提出をすることになっており、東京都のような般・特新規での2通りの扱いにはなっていません。
これは上記の建設業許可事務ガイドラインに従って、全部の業種を特定から一般に変更する場合は、般・特新規ではなく新規になるという扱いであるからだと思われます。(一般⇒特定への変更について、東京都は全業種の変更(つまり「全部般特新規」)であれば、新規と同じ書類の提出となる点は、より厳しいといえますが。)
また、他県では扱いが異なっているので、実際に申請する行政庁に確認しておく必要があります。
例えば以下のようになってます。
神奈川県
(1)「般・特新規」は業種追加と同じ書類の提出をすることになっています。
(2)「特定建設業の専任技術者が不在となり、一般建設業の専任技術者に交替する場合、当該建設業の廃業届を提出した上で、「般・特新規」申請又は「業種追加」申請を行う。」とあります。
埼玉県
(1)「般・特新規」は業種追加と同じ書類の提出をすることになっています。
(2)一般⇒特定への変更、特定⇒一般への変更は新たな申請となります。
特定⇒一般への変更は、従前の許可については廃業届を提出が必要です。(更新許可申請時において財産的基礎要件を欠くに至った場合は除く)
千葉県
(1)「般・特新規」は業種追加と同じ書類の提出をすることになっています。
(2)特定建設業の専任技術者になれる者がいなくなったことにより同じ業種について「特→般」にするときは、特定建設業について廃業届を提出し、新たに一般建設業の許可を取得する必要があります。
なお、「般・特新規」と業種追加では、既に持っている許可番号は変わりません。
関連記事もあわせてお読みください
対応エリア
東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。
お問い合わせ
お電話・ホームページからお問い合わせください!
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。