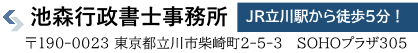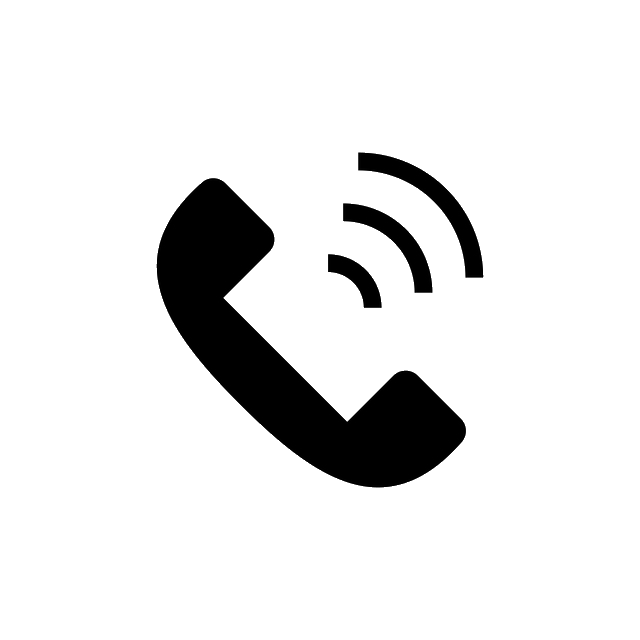�����H�����������Ƃ��Ď���܂ł̗���

�������Ƃ��������Ƃ��Ď��邽�߂ɂ͓��D�ɎQ�����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ē��D�ɎQ�����邽�߂ɂ͓��D�ɎQ�����鎑�i���K�v�ɂȂ�܂��B�������ł͓��D����]����Ǝ҂ɑ��āu�������D�Q�����i�R���v�����{���Ă��܂��B�Ǝ҂͎��O�ɂ��́u�������D�Q�����i�R���v�̐\��������]���銯�����ɒ�o���A�L���i�Җ���ɓo�^����邱�ƂŁA�͂��߂ē��D�ɎQ�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�������D�Q�����i�R����\������ɂ́A�o�c�����R���̌��ʒʒm�����o���Ȃ���Ȃ�܂���B�����āA�o�c�����R����\������ɂ́A���Ƌ����擾���Ă���K�v������܂��B�����̌��Ǝ҂͌o�c�����R����\���ł��܂���B
�����H���ł����Ă������ł���ꍇ�ɂ́A�u�������D�Q�����i�R���v����K�v�͂���܂���B
���̋L���ł́A�����H���̓��D�Q���̊T�v��������Ă��܂��B
�������D�̕��@
����s���{���A�s�������̒n�������̂��������錚�ݍH���i�����H���j��������@�́A�������D�ƂȂ��Ă���A���̗��R�́A�����������ɋƎ҂�I�сA�K���ȉ��i�Ō_������Ԃ��Ƃɂ���܂��B�������D�ɂ́A�傫�������āu��ʋ������D�v�Ɓu�w���������D�v������܂��B��ʋ������D�Ƃ́A�Ǝ҂��w�肹���ɍs�����D�̂��ƂŁA���炩���߁u���D�Q�����i�R���v���s���A���̌��ʂɂ�茚�Ǝ҂̖�����쐬���A���̖���ɓo�^���Ă��錚�݉�Ђ����D�ɎQ�����邱�Ƃ��o���܂��B
�������D�́A�����Ƃ��ė\�艿�i�̐����͈͓̔��ōŒ�D�̍H���Ǝ҂𗎎D�҂Ƃ���Œቿ�i�������D�����ɂ��Ƃ���Ă��܂��B�������A����ł́A�H���̗��s�̊m�ۂ�����ȏꍇ�����邱�Ƃ���A���i�ȊO�̗v�f�i�Z�p�́A�Љ���j�𑍍��I�ɕ]�����ė��D�҂����肷�鑍���]�������̏ꍇ������܂��B
�u�w���������D�v�́A�Ǝ҂𐔎Ђ̋Ǝ҂��w������A��Ԉ����Ƃ��낪���D�ł��邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A�������D�ȊO�̌_����@�Ƃ��ẮA���ӌ_����A��Ђ݂̂��w������Č_�܂��B
���Ȃ݂ɁA�����s�̓��D�Q�����i�������Ǝ҂̐��́A���ׂQ���Ђ��A���̂�����X����������ƂƂ̂��Ƃł��B
�����H���̓��D�Q���܂ł̗���
�����H�������邽�߂ɓ��D�ɎQ������܂ł̗�����ȒP�ɋL�ڂ���Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�P�D���Ƌ����擾����B�i�T�N�ԗL���j
�Q�D�o�c�����R���̐\��������B�i���N�\���j
�R�D�������ɋ������D�Q�����i�R����\�����A�������D�̎��i���擾����B
�@�@�i�L�����Ԃ͂Q�N�ԁB�������A�s�撬���ȂǂłP�N�W�P���̂悤�ȏꍇ������܂��j
�S�D�������D�ɎQ������B
�o�c�����R���A�������D�Q���͂����܂Ō����i�{�傩�璼�ڐ������j�ꍇ�ł����āA�������̏ꍇ�́A�o�c�����R���͕s�v�ł����A���D�Q��������܂���B
���Ƌ��ƌo�c�����R���i�o�R�j�͂Ȃ��K�v�H
���Ƌ��́A�Q�X�̍H���Ǝ했�ɁA���K�͈ȏ�̍H���𐿂��������߂ɕK�v�ƂȂ鋖�ł����A�o�c�����R������ɂ́A���̍H���Ǝ�̌��Ƌ��������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�����āA�����H���̓��D�ɎQ�����邽�߂͌o�c�����R���̕]�_���K�v�ɂȂ�܂��B�o�c�����R���́A���Ǝ҂̌o�c�A�o�c�K�́A�Z�p�́A�Љ�Ȃǂ�R�����_����������̂ŁA�����H���̔���������肷��Ƃ��ɂ��̋Ǝ҂��q�ϓI�ɐR�����邽�߂̂��̂ł��B
�@���u�����H�����҂��璼�ڐ����������Ƃ���҂͌o�c�����R�����Ȃ���Ȃ�
�@�@�Ȃ��v�i���Ɩ@��Q�V���̂Q�R��ꍀ����j�ƒ�߂��Ă��܂��B
�������D�Q�����i�R���Ƃ́H
�u�������D�Q�����i�R���v�ɂ����ẮA�\�������H���Ǝ�ɂ��āA�o�c�����R���̓_���i�q�ϓI�R���j�Ɣ����҂̎�ϓI�R���i�ō������H���o���j�̓_���ɂ��R�����i�̃����N�i�i�t���j�����܂�܂��B���̊i�t���̌��ʂ��L���i�Җ����ɓo�^����܂��B���̓����ʓo�^�i�i�t���j�ɂ���Ďł�������H���̋K�͂����܂�܂��B
�����Q�����i�R���́A�ʍH���̐������͖ړI�ɂ�炸��ɗv�������R�����ڂɂ��ĐR���������̂ł���A�ʍH���̔����̓s�x�A�R�������Ԃ��Ȃ��Ĕ����ҁi�������j�̋Ɩ��̍������E��������}���Ă�����̂Ƃ���Ă��܂��B
�����Q�����i�R���̐\�������́A�����t�Ɛ�����t������܂��B�����s�ł͒����t�͂Q�N�Ɉ�x�ŁA�����s�̏ꍇ�A��N�A�P�P�����{���痂�N�̂P�����܂łƂȂ��Ă���܂��B�i�ڂ����́A�ʓr�A���\����Ă���\���̎�������Q�Ƃ��������j
������t�́A�����t�Ő\�����Ȃ������H���Ǝ҂�A���̑������t�̊��ԈȊO�ɓ��D�Q�����i���K�v�ɂȂ����H���Ǝ҂̕����\���ł��܂��B
�R����́A�����t��������t�������ł��B
�������D�Q�����i�R���̗L�����Ԃ͂Q�N�Ԃ���ʓI�ł��B�A���A����������Ă��̗L�����Ԃ͈قȂ�ꍇ������܂��B
���A���Ƌ��\����o�c�����R���i�o�R�j�̂悤�ɁA�������֔[������萔���͂�����܂���B
�����Ȓ��ɂ����ẮA���Ǝ�ɂ�����o�c�����R���̑����]��l�o�_�ɂ���Ċi�t�����肷��̂���ʓI�ł��B
����A�n�������c�̂ɂ����ẮA�q�ϓI�R�������i�o�c�����R���\���̑����]��l�o�_�j�Ǝ�ϓI�R�������i�e��ڂɂ�����ō������H�����сj�ɂ���Č��肳���̂���ʓI�ł��B�o�c�����R���̕]�_�́A���̊i�t���̌���ɂ����đ�Ϗd�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��̂ŁA���傫���H�������邽�߂ɂ́A����̊i�t�����K�v�ŁA���̂��߂ɂ́A�o�c�����R���̕]�_�A�b�v���d�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�������D�Q�����i�R���̐\���́A�u�d�q�\���v�̏ꍇ�ɂ́A���O�ɁA�d�q�ؖ����A�h�b�J�[�h���[�_�[�̍w���y��PC�̃Z�b�e�B���O���K�v�ɂȂ�܂��B
�d�q�ؖ����A�h�b�J�[�h���[�_�[�́A��̓d�q���D�̎Q���̍ۂɂ��g�p���܂��B
�������D�ւ̎Q��
�e�������̔����v������́A�����z�[���y�[�W��ōs���Ă��܂��B���ƊW�ɓ��������e�АV������ł��f�ڂ���Ă��܂��B����ł́A�H�������E�{�H�ꏊ���̑��ɁA�ΏۂƂȂ�i�t�i�����N�j�Ǝ�t���ԁA���D�����f�ڂ���Ă��܂��B���̎�t���ԓ��Ɋ�]�[���o���܂��B���݂ł͑����̊������Łu�d�q���D�v����������Ă��܂��B
�ŋ߂ł͍Œᐧ�����i�ɂ��ė��D�����܂ł͌��\���Ȃ��Ƃ������Ƃ���ʓI�ŁA���ς�����z�̎Z�o�ɂ������ẮA��p�����ςݏグ�Čv�Z����u�ώZ�v�Ƃ������@�ɂ��܂��B�����҂�����D�O�ɒ����H�����e�̎����Ɋ�Â��āA�H�����z��ώZ���A���ς�����쐬���܂��B�܂��A�����ґ��ōŒᗎ�D���i�����߂Ă���̂ŁA�Œᗎ�D���i�������Ȃ����z���Z�o���Ȃ���Ύ��邱�Ƃ͂ł��܂���B���D�����ꍇ�͔����҂ƍH�������_������킵�Ď{�H�������ƂɂȂ�܂��B
��ʋ������D�A�w���������D�A�v���|�[�U�������Ƃ́H
��ʋ������D
��ʋ������D�́A���D���i���擾���Ă���Ǝ҂Ȃ�N�ł��Q���ł�������ł��B
�Q����]�̋Ǝғ��m�ŋ����ɎQ�����āA���D�҂����肵�܂��B
�w���������D
�w���������D�́A�������⎩���̂����炩���ߑI�Ǝ҂����ŋ������D���s�������ł��B
�Č��ɑ��āA���̎��т�Z�p�͂�����ƌ��Ȃ��ꂽ�Ǝ҂������A���D�ɎQ���ł���Ƃ��낪�����ł��B
�E���������Ƃ����Ȃ���ʋ������D�ɂ���K�v���Ȃ��ꍇ
�E?�_��̐�����ړI���ʋ������D�ɓK���Ȃ��ꍇ
�E�s�����ȋƎ҂��Q������̂������ꍇ�i�k���h�~�E���Љ�͂Ȃǁj
�E?����������������ȓ���ȍH���Č�
�w���������D�͊��������Ǝ҂��w�����邽�߁A���т����Ȃ��V�K�Ǝ҂͑I�o����Â炢�V�X�e���ł��B
���D���S�҂̂����́A���i���N���A���Ă���ΒN�ł��Q���ł����ʋ������D��I�т܂��傤�B
��ʋ������D�ɂ���ė��D�����Č��ɑ��č��i���ȕ��i��H���Ȃǂ�ł���A�₪�Ďw���������D�őI���\���͍��܂�܂��B
�v���|�[�U�������i��拣�����D�j
�v���|�[�U�������́A�����҂�����\�Z�͈͓̔��Ŋ���Z�p��Ă����Ă��炤�����ł��B
���ӌ_��
���ӌ_��͓��D�ɂ�鋣�������Ȃ����āA�X���[�Y�ɓ���̋Ǝ҂ƌ_������Ԃ��߂̗�O�I�ȕ����ł��B
���ӌ_��������́A���z�̈Č��⋣�������Ȃ��_��A�ً}���������Č����Ώۂł��B
�ЊQ�̉e���ʼn͐�̒�h�����Ă��܂����A���H�זv�ňꕔ�n��̏Z�����Ǘ����Ă���ȂǁA�ꍏ�������������K�v���Ɣ��f�����ΐ��ӌ_������܂��B
�o�c�����R���̑ΏۂƂȂ�u�����H���v�Ƃ�
�o�c�����R�����Ȃ���ΐ����������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���Ă���H���i=�����H���j�́A���̂Ƃ���A(1)�Ɓi2)�̗����ɊY������ꍇ�ł��B
(1)�H���P���̐�������̊z���T�O�O���~�ȏ�i���z�ꎮ�H���̏ꍇ�͂P�C�T�O�O���~�ȏ�j��
�@����
(2)�����҂����̂����ꂩ�ł���{�ݖ��͍H�앨�Ɋւ��錚�ݍH��
�@��
�A�n�������c��
�B�@�l�Ŗ@�ʕ\���Ɍf��������@�l�i�n�������c�̂͏����j
�C��L�ɏ�������̂Ƃ��č��y��ʏȗ߂Œ�߂�@�l
�����ۋ�`������ЁA���Q���N��Q�⏞�\�h����A��s�������H������ЁA���h�c���������ЊQ�⏞�����ϊ���A�n�����n�S������A�����n���S������ЁA�@�����p���f���H�̌��݂Ɋւ�����ʑ[�u�@�@(���a�Z�\��N�@����l�\�܍�)�����ꍀ�@�ɋK�肷�铌���p���f���H���ݎ��ƎҁA�Ɨ��s���@�l�Ȋw�Z�p�U���@�\�A�Ɨ��s���@�l�ΘJ�ґސE�����ϋ@�\�A�Ɨ��s���@�l�V�G�l���M�[�E�Y�ƋZ�p�����J���@�\�A�Ɨ��s���@�l������Ɗ�Ր����@�\�A�Ɨ��s���@�l���{���q�͌����J���@�\�A�Ɨ��s���@�l�_�ƎҔN������A�Ɨ��s���@�l�����w�������A�����{�������H������ЁA���c���ۋ�`������ЁA�����{�������H������ЁA���{�����S���Ɗ�����ЁA���{���^�����ԐU����A���{���]�ԐU����A���{�����w�Z�U���E���ώ��ƒc�A���{�����Y�Ɗ�����ЁA�@���{�d�M�d�b������Г��Ɋւ���@���@(���a�\��N�@���攪�\�܍�)�����ꍀ�@�ɋK�肷���Ћy�ѓ����@�ɋK�肷��n���ЁA�@�_�ы��ƒc�̐E�����ϑg���A��_�������H������ЁA�����{�������H������ЁA�{�B�l���A���������H������Е��тɁA�@���q�S��������Ћy�ѓ��{�ݕ��S��������ЂɊւ���@���@(���a�Z�\��N�@���攪�\����)�����O���@�ɋK�肷����
�������A���̐ݍH���ɂ��ẮA�Ώۂ��珜����܂��B
[1]��h�̌���A���H�̖��v�A�d�C�ݔ��̌̏Ⴛ�̑��{�ݖ��͍H�앨�̔j��A���v���ŁA�������u����Ƃ��́A��������Q���邨����̂�����̂ɂ���ĕK�v
�������}�̌��ݍH��
[2] [1]�Ɍf������̂̂ق��A�o�c�����R�����Ă��Ȃ����Ǝ҂������҂��璼�ڐ����������Ƃɂ��ċً}�̕K�v���̑���ނȂ����������̂Ƃ��č��y
��ʑ�b���w�肷�錚�ݍH���j
���������ł̑�s�T�[�r�X���e�ɂ���
| �\�����e | ��p�E�萔�� |
���������萔�� |
���v���z | |
| �d�q�ؖ����擾 |
�@�d�q�ؖ����F66,000�~�i�T�N�ԗL�����Ԃ̏ꍇ�j |
30,000�~�` | 30,000�~�`�{���� | |
|
���D�Q�����i�\�� |
�Ȃ� �i���I�ؖ����萔���͕ʓr�v�j |
50,000�~�` | 50,000�~�`�{���� | |
�܂Ƃ�
���Ƌ��A�o�R�A�������D�Q�����i�̐\���ɂ��Ă��̊W���ɏd�_�������ĉ�����܂����B���傫�������H�������邽�߂ɂ́A�o�R�̕]�_�A�b�v��}�邱�Ƃ��������邱�ƂƁA�����H�����̍ō��z���i�t���̑傫�ȗv���ƂȂ�܂��B�������A�i�t���ł̍H���Ǝ�̋敪�́A���Ƌ��A�o�R�ł̋敪�ɔ�ׂĂ��ׂ��ȋ敪�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�ǂ̍H���Ǝ�œ��D�ɎQ������̂����A���E�o�R�ł̋Ǝ�Ƃ悭��ׂĂ������ق����悢�ł��傤�B
����ɂ��ẮA�ʂ̋L���ʼn�����Ă��܂��̂ŎQ�Ƃ��Ă݂Ă��������B
�֘A�L�������킹�Ă��ǂ݂�������
 �@�o�ǂƂ�
�@�o�ǂƂ�
�Ή��G���A
�����s�敔:
������A�r���A����A�]�ː��A��c��A������A�k��A�]����A�i���A�a�J��A�V�h��A������A�n�c��A���c�J��A�䓌��A������A���c��A�L����A�����A���n��A������A�`��A�ڍ���
�����n��:
�����s�A�������s�A���s�A�~�s�A�����s�A�����s�A������s�A�������s�A�����s�A���]�s�A����s�A�����s�A���z�s�A�������s�A�����q�s�A�H���s�A���v���Ďs�A�����R�s�A����a�s�A����s�A�{���s�A�����s�A���c�s�A�O��s�A������s�A�������R�s�A���������A���̏o���A���䒬�A�w����
����ȑΉ��n��ł��B
���₢���킹
���d�b�E�z�[���y�[�W���炨�₢���킹���������I
�s�����m�͖@��(�s�����m�@��12��)�ɂ����`��������܂��̂ň��S���Č䑊�k���������B�B
���d�b�E�z�[���y�[�W���炨�₢���킹�͖����ł��B

��t���ԁF�@����9:00-18:00
�d�b�E���[���Ō�\��������Γy�E���E�j�����Ή��������܂��B