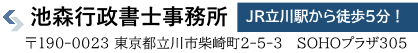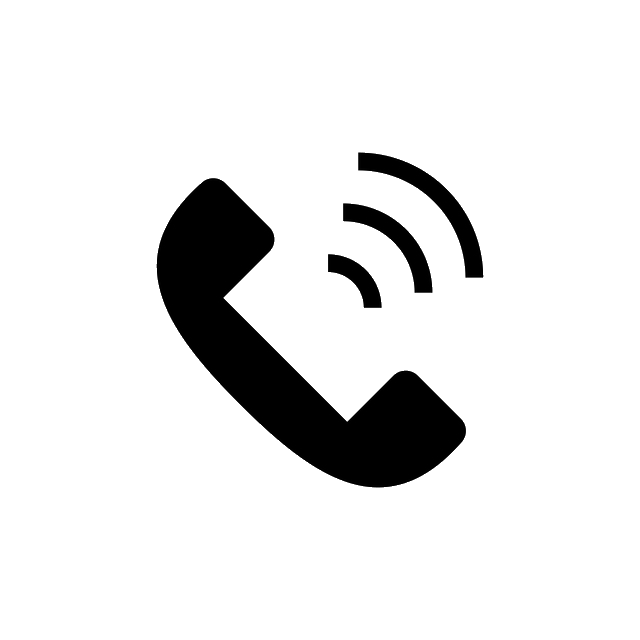産業廃棄物とは?

廃棄物処理法で定義されている「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいいます。
また、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、法により「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理責任や処理方法が区分されています。一般廃棄物の処理責任は基本的に市町村が負い、産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負うということになっています。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、特定の事業活動に伴って排出される法令で定められた20種類の廃棄物のことです。例えば、向上での生産過程における端材や不良品、建設現場でのコンクリートの残り、農業生産に伴う不要な資材や農薬容器などが該当します。
事業活動によって生じた廃棄物であっても、法令で定められた20種類に該当しなければ一般廃棄物となる点は覚えておきましょう。産業廃棄物は、その性質に応じて適切な処理が必要とされており,産業廃棄物処理法によって規制されています。
一般廃棄物とは?
一般廃棄物は産業廃棄物に該当しない廃棄物であり、一般家庭から排出されるゴミや粗大ゴミなどです。事業活動においても、法令で定められた20種類の廃棄物に該当しなければ一般廃棄物となります。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、自治体ごとのルールに併せて廃棄物の処理を依頼する形になります。
産業廃棄物の種類
法令で定められた20種類の廃棄物について、具体例を表形式で解説します。そのなかでも、大きく2つに分けられるため、それぞれ見ていきましょう。
(1)あらゆる事業活動で排出されるもの
あらゆる事業活動で排出される産業廃棄物としては次のとおりです。
| 産業廃棄物の種類 | 例 | |
|---|---|---|
| 1 | 燃えがら | 石炭殻、焼却炉の残灰など |
| 2 | 汚泥 | 排水処理後・各種製造業生産過程で排出された泥上のもの、洗車場汚泥、建設汚泥など |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄湯、切削油、溶剤など |
| 4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃塩酸、各種有機廃酸類などのすべての酸性廃液 |
| 5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど、すべての合成高分子系化合物 |
| 7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
| 8 | 金属くず | 鉄鋼、被鉄筋族の破片、研磨くず、切削屑など |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くずなど |
| 10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
| 11 | がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片など、これらに類する不要物 |
| 12 | ばいじん | 気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
(2)排出する業種が限定されるもの
特定の業種から排出される廃棄物のなかで、産業廃棄物と指定されているものは次のとおりです。
| 産業廃棄物の種類 | 例 | |
|---|---|---|
| 13 | 紙くず | 建設業・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず |
| 14 | 木くず | 建設業、木材/木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木材編、おがくず、バーク類などの貨物の流通のために使用したパレット類 |
| 15 | 繊維くず | 建設業、衣類その他繊維製品製造業以外から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
| 16 | 動植物性残さ | 衣料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物 |
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかわる固形状の不要物 |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどのふん尿 |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどの死体 |
(3)その他
| 産業廃棄物の種類 | 例 | |
|---|---|---|
| 20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの | 有害汚泥のコンクリート固形化物 |
産業廃棄物の処理方法と流れ
排出事業者
廃棄物処理法では、「産業廃棄物の排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。「自らの責任において適正に処理する」とは、排出事業者が「自ら処理する場合」と「処理業者に処理を委託する場合」があります。
原則は、排出事業者が責任を持って産業廃棄物の保管、運搬、処分をしなくてはなりません(排出事業者責任)。その際には産業廃棄物の※処理基準を遵守しなくてはなりません。もし基準を外れた処理をした場合、罰金等の刑罰や行政処分が科せられます。
なお、産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者は、原則として自らが受けた処理業務を別の処理業者に任せて(再委託)はいけないとされています。これは再委託により責任の所在があいまいになることが、不法投棄等に結びつくおそれがあると考えられているからです。
排出事業者は産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄
物処理業者に交付し、最終処分まで確認することが義務付けされています。
建設工事から生ずる廃棄物の排出事業者
建設工事で発生した廃棄物の排出事業者は、発注者から直接工事の注文を受けた元請業者であると法律で定められています。
排出業者である元請は、建設現場で発生した廃棄物を収集運搬業の許可なく自社運搬出来ます。もちろん自社運搬する場合でも、車両の表示義務、書面の携帯および収集・運搬基準の遵守は必要となります。また、排出された廃棄物を自社の事業場で仮置きをする場合でも、積替え保管の許可は必要ありません。
下請け業者が施工に携わる工事にあっては、建設廃棄物の排出事業者は誰になるのでしょうか?その場合でも、下請け業者は排出事業者とならず、発注者から最初に工事の注文を受けた元請業者が排出事業者となります。
※但し例外があって、一定の条件をすべて満たす場合には、下請け業者も排出事業者となることができます。
収集運搬(積替え保管除く)
産業廃棄物の収集運搬とは、「排出事業者から排出された産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場まで運搬すること」です。この収集運搬を業として行う者が収集運搬業者です
収集運搬業者の役割は、「排出事業者から委託された産業廃棄物を、法と委託契約に従い、
性状を変えることなく、飛散、流出を伴わないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬する
こと」です。
収集運搬業を営むには、都道府県知事等の許可が必要となります。
取扱う産業廃棄物の種類によって産業廃棄物収
集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の二つに区分されています。
収取・運搬は、排出事業者が自ら実施する場合と、収集・運搬業者に委託する場合が考えられます。排出事業者が自ら実施する場合には、産業廃棄物の収集・運搬にかかわる基準を遵守しなければなりません。また、収集・運搬事業者に委託する場合には、委託基準を遵守する必要があります。
収集運搬(積替え保管含む)
産業廃棄物の収集運搬においては、収集してから中間処理施設に直接運搬することが原則ですが、運搬効率を上げるために、収集運搬に付随して積替えや保管を行うことが認められています。積替え保管を行うに際しては、産業廃棄物の収集運搬基準、保管基準に基づいて行う必要があります。
上記の基準の他、都道府県等では、その地域の実情にあわせて、独自に積替え保管施設の基準となる指針を設けていることがあります。法令で定めている基準に加えて、立地、構造、維持管理に関する基準を設けるなど、より詳細な項目を定めています。
中間処理
処理事業者のもとに集められた産業廃棄物は種類に応じて中間処理されます。中間処理は処理事業者のもとで、焼却や脱水・分別などを行う処理です。中間処理によって産業廃棄物そのものの量を減らしたり、分別することでリサイクル(再生処理)を実施したりします。
最終処分
産業廃棄物は最終処分として、埋立処分と海洋投入処分と再生の3つの方法が規定されています。また、これらの方法で処分を行うことが可能な場所も規定しています。なお、海洋投入処分は条約により原則禁止とされています。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
東京都多摩地区の建設業許可取得、経営事項審査、会社設立はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!
迅速・丁寧にお悩みにお答えいたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
.jpg)