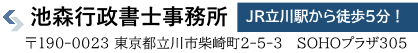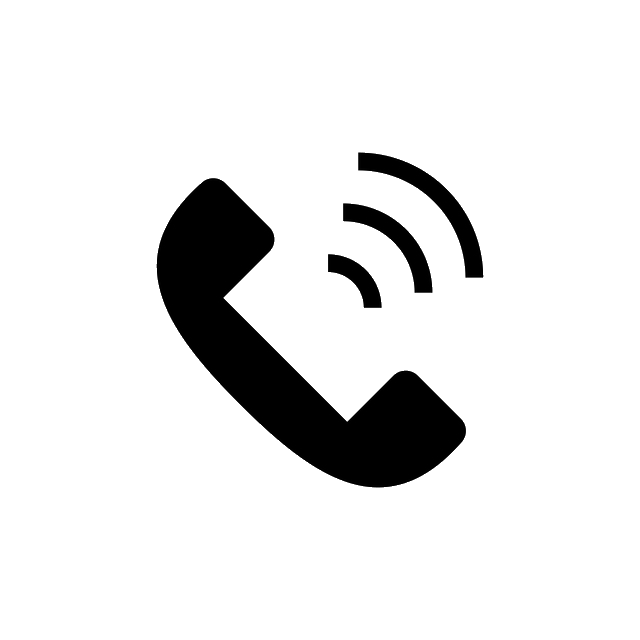産業廃棄物の収集運搬業許可の申請について

産業廃棄物を他者から委託されて運搬する場合、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の基本から、取得に必要な条件、申請の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託された産業廃棄物を収集・運搬するために必要な行政上の許可です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づき、都道府県知事(政令市は市長)が許可を行います。
この許可を取得することで、廃棄物処理業の一環として、工場や建設現場から出る廃棄物を運搬し、処分場や中間処理施設まで届けることが可能になります。
産業廃棄物収集運搬業許可については、廃棄物を「積む地」と「下ろす地」の両方の都道府県知事の許可が必要となります。
② 産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可は、取り扱う産業廃棄物の種類について取得する必要があります。
新規許可の取得後に、取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたい場合は、「変更届出」ではなく、「事業範囲の変更許可申請」をしなければなりません。
申請の種類
①新規許可 区分ごとに初めて許可を取得しようとする場合
②更新許可 従前の許可を継続する場合
③変更許可1)取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
2 )取り扱う産業廃棄物の限定を解除する場合
3 )業の区分を拡大する場合
4 )処分の方法を変更・追加する場合
許可の有効期間
5年間(平成22年改正法により創設された優良産廃処理業者認定制度において、優良基準に適合していると認められるときは、7年になります。
収集運搬業の区分
①産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
収集した廃棄物を一時的に保管せず、直接処分場へ運搬する場合です。
②産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
収集運搬の途中で、自社の倉庫等で廃棄物を一時的に積替え保管した後に、中間処理施設に運搬する場合です。
運搬範囲・申請先
1つの政令市の範囲を超えて運搬する場合・・・各都道府県に申請
1つの政令市内でのみ運搬する場合・・・該当する政令市に申請
なお、「積替え保管を含む」許可を申請する場合は、当該積替え保管場所がある政令市の許可も必要です(保管場所が政令市ではない市町村であれば都道府県の許可のみで足ります)。
また、先述の通り、荷積みと荷下ろしが異なる都道府県の場合は、両方の都道府県で許可を取る必要があります(通過するだけの都道府県がある場合、その都道府県の許可は不要です)。
運搬車両について
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。
◇車両の使用権原
①使用者が申請者と一致していること
②使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致していること
※下記車両の登録は認められません。
・レンタル車両(借受契約等で借りている車両)
・トレーラ及びセミトレーラ(容器として取り扱います。)
◇ディーゼル車規制
①東京都では、PM(粒子状物質)の排出規制が行われ、排出基準に満たない車両は東京都内を走行できません。この場合は、買替えまたは粒子状物質減少装置(DPF)を装着しなければなりません。
②埼玉県・千葉県・神奈川県でも同様な規制があります。
◇土砂等禁止車
車検証の備考欄に、土砂等運搬禁止車と記載がある場合には、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、汚泥は運搬できません
◇車両の表示義務ほか
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令定める書面を備え付けておくことが義務付けられています。
<表示の内容>
① 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
② 許可業者の氏名又は名称
③ 統一許可番号(下6けたは全国統一されている)
<備えるべき書面>
①産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
②産業廃棄物管理票(マニフェスト)
◇車両の保管場所の使用権原
所 有 土地の登記簿謄本又は自動車保管場所証明書(本人控え写し)
賃貸借 賃貸借契約書又は自動車保管場所証明書(本人控え写し)
能力基準~講習会受講
許可申請には、個人の場合は申請者本人、法人の場合には代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。すべての都道府県等が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターでの講習会を実施しています。
能力基準~経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
・債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。
・債務超過ではあるが、事業の利益が計上され将来債務超過が確実に解消できるという申請者にあっては、「債務超過の理由」「経営改善対策」「記入者氏名等」を記載する中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成したもの等の書類の提出を求めて、経理的基礎を有するかの審査資料とされます。
欠格要件
申請者の役員、政令6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び株主5%以上の(出資者)が次に定める欠格条項に該当しないこと。
【欠格条項(抜粋)】
①成年被後見人、被保佐人、破産者
②禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③次の法律で罰金以上の刑で、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を5年を経過しない者
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・公害関係諸法規(*)
(以下、略)
許可申請書の作成要領
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(東京都)の内容とポイントを紹介します。
1.事業の範囲
取り扱う産業廃棄物の種類とその産業廃棄物に石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれるか。
また、積替え保管を行うかどうかの別事務所及び事業場の所在地都内にある産業廃棄物に係る事業を行う事務所・事業場を記載する。
事業の用に供する施設の種類及び数量運搬車両と容器について記載する。
2.変更事項確認書・新旧役員等対照表(更新申請又は変更申請で使用)
※直前の申請又は変更届以降の変更事項の有無を確認するもの。
変更事項がある場合には、変更届と同様に必要な確認書類を添付。
3.事業計画の概要
4.運搬車両の写真(カラー)
※車両は、前面(真正面からナンバープレートが読み取れるように)及び側面(真横から車両全体が分かるように)から撮影。
※産業廃棄物収集運搬車は、車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」、「会社名(事業者名)」、「許可番号の下6桁」を表示すること。
車体の表示が読み取れない場合には、別途、当該部分を接写した写真を3枚目として添付すること。
5.運搬容器等の写真(カラー)
※更新許可申請の場合、継続して使用する容器は提出不要ですが、注1)の場合は必要。
注1)更新許可申請で、継続して使用する容器であっても、収める廃棄物が違う場合、新たに泥状の石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合は、最新版の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」で求める容器の写真を添付すること。
注2)・ 届出者が実際に所有している容器を、会社名の入った看板や都に登録してある車両(ナンバープレートや産業廃棄物収集運搬車の表示)の前等で撮影すること。パンフレットやホームページ上の写真は不可。容器等の全体が分かるように、1種類につき1枚撮影。
オープンドラム缶は、留め金具及び蓋を本体から外し、状態が確認できるようにに撮影。
6.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を添付している場合は不要。
7.資産に関する調書(個人用)
8.誓約書(欠格条項に該当しない旨)
9.定款の写し
※定款の末尾には、原本証明を忘れずに付すこと。
※事業目的に産業廃棄物処理業がない場合には、事前に相談しておくこと。
10.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
11.住民票抄本
※申請者、役員等(*1)、5%以上の株主又は出資者、政令使用人について必要(本籍地記載のもの、マイナンバーが記載されていないもの、続柄は不要)
12.登記されていないことの証明書(成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書)等
※申請者、役員等(*1)、5%以上の株主又は出資者、政令使用人について必要
13.政令使用人に関する証明書
※当該使用人がいない場合は不要
14.許可証のコピー
※新規の場合は既に取得している場合は、その許可証(他道府県市の分など)
※更新の場合は更新する許可に係る東京都許可証
※八王子市の産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を含む)の許可を有する場合は当該許可証
15.貸借対照表(直近3年分)
16.損益計算書(直近3年分)
17.株主資本等変動計算書(直近3年分)
18.個別注記表(直近3年分)
19.法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
20.所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
※ 個人申請の場合
21.経理的基礎を有することの説明書及び記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)
※該当者のみ提出が必要な書類。該当するか否かは、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引p.12「(4)財政能力」のチェックフローで確認すること。
22.講習会修了証の写し
※修了日及び有効期間の確認。
23.ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の自動車検査証の場合は車検証の写し(使用する全車両)
※ 有効期間、使用者欄、ディーゼル規制などに注意する。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
東京都多摩地区の建設業許可取得、経営事項審査、会社設立はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!
迅速・丁寧にお悩みにお答えいたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
.jpg)